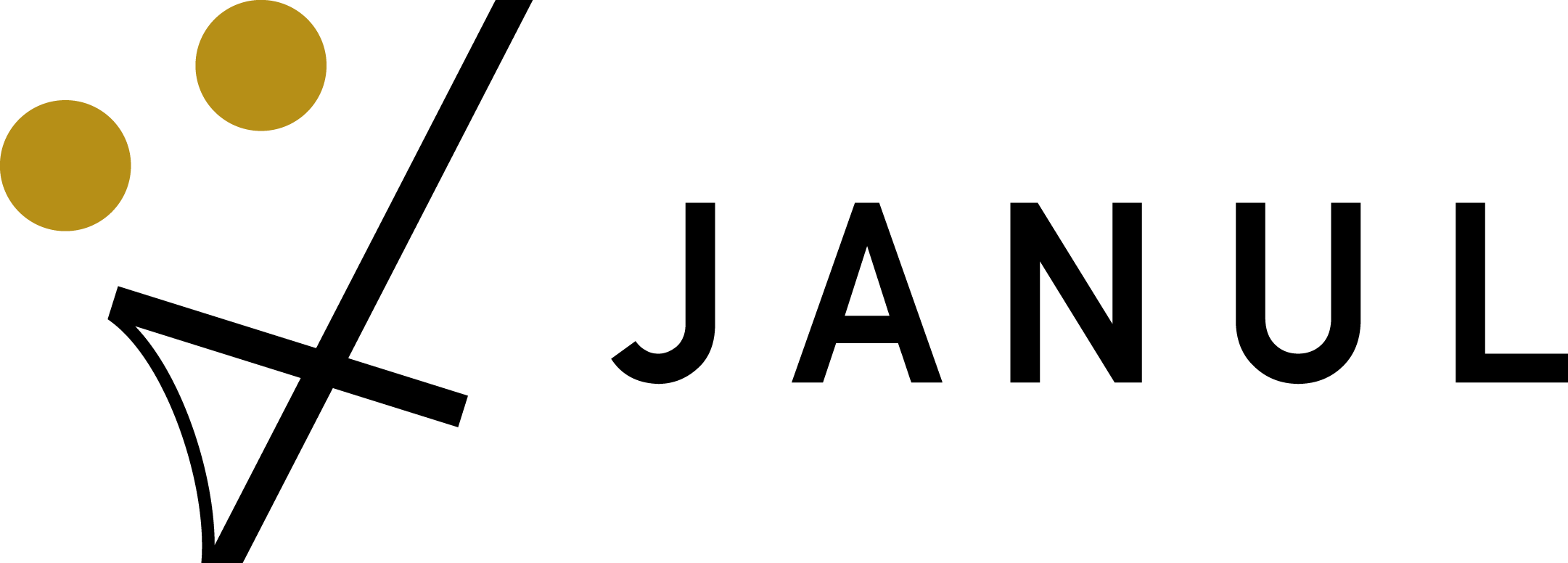宮崎大学教育学部教授・附属図書館前副館長の中村佳文先生、宮崎大学附属図書館管理係の中田憲宏係長に、図書館に関係する多様なステイクホルダーにより実施された「プロジェクションマッピング短歌会」の母体となった「創発WG(学生活動・創発・支援)(以下、「創発WG」)による活動」についてお話をお伺いしました。
「創発WGによる活動」について
Q. 創発WGによる活動のきっかけはどのようなものだったのでしょうか?
中村: 最初のきっかけは図書館の改修です。フロアごとに異なるコンセプトを立てて、その一つにクリエイティブな空間を設計しました。さらに、改修で空間を構築しただけでは不十分で、図書館の中で創造的かつ課題解決的に根付いていく空間にしたいと考えました。そこで、当時副館長であった私が創発WGを設けて、図書館の運営委員会の先生に限らず、教員・職員・学生など広く様々な人に参画してもらい、クリエイティブな空間の活用を考え、図書館のリニューアルに併せて創発活動を開始する予定でした。ところが、図書館のリニューアルが2020年のコロナ禍に当たってしまい、出鼻をくじかれることになりました。この時はオンラインを活用してワーキンググループの活動を継続して行いました。このような状況で、創発WGの活動は、副館長・図書館から始まり、様々な分野のこのような活動に興味のある方に参画してもらいたく、私からお声がけしたり、自主的に参加していただいた先生・学生を巻き込み、図書館と教員で連携をしながらスタートしました。

(写真1)オンラインによる打ち合わせの様子
Q. 大学全体として図書館に協力して活動を進めようといった雰囲気が感じられたのですが、いかがでしょうか。
中村: 当時の館長兼副学長が、図書館の改修計画とともに学生の創発という活動、教育の在り方に深い関心と意欲を持たれていたこともあり、館長を通じた人のつながりを元に創発にご協力をいただけそうな先生方にお声がけをすることができました。
また、図書館は学内中心部に位置しており、図書館の本来の機能だけではなく、学内の知が出会う場所といった、キャンパス内での位置づけについての構想も改修計画の中に含まれており、大学の執行部とも意識をあわせて創発を根付かせていくという方向性が定まったと思っています。
Q. 創発WGによる活動の具体的な取組として、プロジェクションマッピング短歌会が開催された流れはどのようなものだったのでしょうか。
中村: 宮崎大学には、「とっても元気!宮大チャレンジ・プログラム」という、社会でリーダーとして活躍する宮大生の企画する力や実施する力を高めるためのプログラムがあり、例えば学生が地域貢献活動など地域に特化した研究などで資金を獲得してプロジェクトに取り組むことができます。このチャレンジプログラムの担当の先生に加えて、光学の研究をされている工学研究科の先生の研究室に所属する大学院生、私が顧問をしている宮崎大学短歌会の学生が創発WGに参加していました。
創発WGのなかで、工学研究科の大学院生から、「チャレンジプログラムでプロジェクションマッピングを作りたいが、どのような素材が魅力的か素材選びが難しい」という話題が出ました。そこで、宮崎県は「日本一の短歌県」を目指しており、若山牧水の出身地で牧水賞や短歌甲子園を開催するなど、短歌に力を入れているという話題になり、短歌の情景のプロジェクションマッピングを用いて小学生などと学べるようにしたら面白いのではないかという結論になりました。結果として、光学の研究、教科教育学、宮崎大学短歌会、そして宮崎という地域の特性がつながり、文理融合のプロジェクトに結びつきました。

(写真2)プロジェクションマッピング短歌会の様子
Q. 図書館でプロジェクションマッピングを行うというのは、予算面などでハードルが高いようにも感じますが、その点はどのようにされたのでしょうか。
中村: チャレンジプログラムに採択された予算をベースに、プロジェクターなどの機材は先生方が所有されていたものをプロジェクションマッピングチームに貸出をしてもらい利用してもらいました。図書館は、場所の提供、環境整備を行うという形で協力をしました。
その後、宮崎県の文化事業にも参画し、宮崎科学技術館で『注文の多い料理店』のプロジェクションマッピングの公開も行い、子どもたちや親御さんにも観ていただくことができました。その際にも予算を獲得することができており、うまく発展することができたと思います。
現在(いま)
Q. 創発WGによる活動において、図書館員の役割はどのようなものでしょうか?
中田: 図書館職員は、事務局のような立ち位置で、連絡調整等を行うという位置づけになっています。また、活動内容が決まれば、 図書館内での活動環境を整えてサポートを行うほか、図書館の利用条件等の確認なども行って、参画・協力するという形になっています。創発WGには、当時、管理係の係員として参加しましたが、当時から他係の職員も含め図書館職員全体として参画しています。
Q. 創発WGによる活動の以前と以後で、利用者である教員や院生には変化がありましたか?
中田: 学生の認識として、今までイメージしていた図書館とは違う使い方をすることができるという認識が広がったと思います。クリエイティブな空間を使った課外活動が積極的に行われるようになり、具体的には教育実習の練習、ボランティア活動のミーティング等が行われています。
中村: 創発を目的にしていますので、教員がむりやり維持するのではなく、自主的な学びとして展開をしていると考えています。例えば、農学部・工学部の所属で、教職を目指す学生さんたちに教職関連の情報が行き届いていないということでしたので、教育学部の学生さんと農学部・工学部の同じく教職を目指す学生さんがつながれるとよいと思い、採用試験対策の情報などを共有するような活動をしています。
また、私が顧問を務めている短歌会でも、月2回程度歌会を開催しており、2021年に開催された「第35回国民文化祭・みやざき」の短歌企画も、図書館1階のワークショップコートで開催しました。このような教員採用や地域に関連した取組などに、学生さんが目を向けるようになってきていると思います。
Q. 支援事業の開始以前と以後で、図書館の職員には変化がありましたでしょうか?
中田: 今回のような取組を行うことで、図書館でできることの認識について、幅が広がったのではないかと思います。 また、学生さんや先生方と一緒になって何か一つのものを作り上げるというところで、図書館以外、外の人材とのコミュニケーションで新たな取組が生まれるということが実感できました。
未来(これから)
Q. 支援事業は、今後、どのようなことをしていきたいと考えていますか?
中村: このような活動のエンジン、牽引する力について考えていて、現在の図書館の取組のように学生さんの流れや交流などを元に、従来の講義の枠を超えて実現できないかと思っています。また、私の専門の短歌という点では、若い学生が好むコンテンツ、例えばショート動画のような形でのコンテンツ提供にも取り組んでみたいと考えています。ショート動画を入り口にして、短歌の深い世界を知ってもらう。このような仕掛けを全学の科目で行うようなことを、個人的な未来像として考えています。
また、地域の特色を活かすことも地方大学の大きな役割ですので、県内の若山牧水記念文学館の展示を図書館の一角で行ったりしており、このような取組も講義や学生の興味の触発・主体的な学びにつながり、ひいては取組をしている図書館に集まろうと学生さんが意識するようになると考えています。
中田: 現在、宮崎大学の中では図書館に限らず、様々なアイデアがあり、そういったところと連携して図書館で何かを取り組むというのもよいかと思っています。 図書館だけが主体となる必要はなくて、とにかく図書館でできることを提案していくことも大事なポイントではないかと考えています。
中村: もう1点、追加でお話しするとオンラインの活用も重要です。コロナ禍がある程度落ち着いてきて、活用が下火になりつつあるように思うのですが、仕組みは導入されているので、もっとオンラインを活用するとよいと思います。例えば、学外の方を講師に招聘するオンラインセミナーの開催などがあります。宮崎大学木花キャンパスは、市中心部よりはちょっと離れているので、セミナー実施の弊害にならないようにオンラインを活用できると創発の二次的展開にもつながるのではないかと考えています。
「創発WG(学生活動・創発・支援)による活動」担当窓口および連絡先:
宮崎大学附属図書館管理係
lib-shomu@of.miyazaki-u.ac.jp
(@を半角にして送信してください)
--------
「ビジョン2025重点領域2企画」担当者チーム
電気通信大学学術情報課 上野 友稔(取材・文責)
取材日:2025年2月17日(月)